こんばんは!
いつも応援していただき、ありがとうございます。
apa(あぱ)です(^^)
今日は『AI頼り切りのリスク』について書いていきます。
おかしいなAI
うーん、おかしいな・・・
AIの言う通りにやっているはずなのに、思うようにいかないな。
どうしてだろう。
どうしたんですか?
a男さん。
思うようにいかない?
なにかあったんですか?
あ、apaさん。
そうなんです。
WordPressの設定とかでわからないことがあって、AIに質問したんですけど、良い回答が返ってこなくて悩んでいたんです。
というか、結構思い通りの結果を出せずに悩んでいたんです。
AIの言う通りにすれば解決するかと思っていたんですけど、案外そうじゃないのかなと考えていました。
なるほど。
確かに。
AIを使うことは大切ですが、全てそれが正しいとは限りませんからね。
AIを使って作業に臨んでいる方は多いと思います。作業だけじゃなくて、AIを使って仕事を優位に進める努力をしている方も多いと思います。
僕自身、AIはバリバリ使っているのですが、AIも使い方が難しいなと最近感じたりします。
何よりそう感じるのは、「頼り切りのリスク」。
頼り切ってしまうと人間は簡単に考えることを放棄してしまいます。
当たり前の話ですが、考えることを放棄してしまうと目的を達成することができなくなってしまいます。
一応、このブログはSEO向けのブログなので、SEOのことを考えると、目的は結果を出すこと。
あまり良くない言葉づかいをすると、稼ぐこと。
それ以外の問題はすべて手段に過ぎません。しかしAIはそうした手段に対しては強い。
目前の問題を解決したり、目前の目標を達成することはできても、最終的な目的へは導いてくれません。
そのあたりは、人間が自分で考えないとならない部分ですが、
そんなのは書くまでもなく当たり前のことではありますが、どうしても。
AIに頼り切りになっていると、そんな当たり前のことすらわからなくなってしまいます。
便利だからつい使ってしまうAIも、
使うから頼るにならないように注意する必要があります。
AI頼り切りのリスク
おかしいな・・・
AIを使えばもっと完璧に問題を解決できると思っていたのにな・・・
違うのかな・・・
その気持ち、すごくよくわかります。
確かに、AIを使えば、もっと問題をスムーズに解決できると思っていたのに、意外と苦労したりすることってありますよね。
結局のところ、AIに頼り切りになるのは、様々なリスクを孕んでいると言えるのかもしれません。
AIは便利だけど使い方を間違えると様々な問題が生じます。
自分で考えなくなること
最大のリスクは自分で考えなくなること。
偉そうなことを言うつもりはまったくなく、
自分自身、そういう傾向があり、ちょっと頭を抱えていました。
自分で考えなくなることは本当に危険です。
そしてAIは残念ながら、当然ながら。
その責任を折ってくれません。
サクッと削除、しちゃいましょう
例えば僕が運用している別の「ジャズブログ」。
基本、僕の趣味のレコードの記録をまとめているようなブログなんですけど、
そこにおいて、具体的には忘れましたが、ある問題が生じました。
そのときにその原因と対策をClaudeに訪ねたところ、
「それは、一つの記事で複数のカテゴリを選択していることが原因です。それはよくありません。」
と言われました。
具体的には、
一つの記事に対して「アーティスト名」のカテゴリと「楽器名」のカテゴリに従属させていました。
今考えれば、確かに、2つともメインカテゴリとするのは良くなく、どちらかはサブカテゴリという扱いにしたほうがいいという意味だったのかもしれませんが、
その中で、
「楽器のカテゴリは不要なのでサクッと削除しちゃいましょう。」
と言ってきました。
本当にそういったんですよ。
「サクッと削除しちゃいましょう。」
と。
で、あろうことか、「そこまで言い切るのであれば・・・」と鵜呑みにしてしまう、楽器のカテゴリをすべて削除してしまいました。
しかも問題は解決しませんでした。
結局問題は別のプラグインに問題があることが発覚。
もちろん、AIを攻めても、「申し訳ございませんでした。」「気をつけます。」の一点張りで、元の状態に戻してくれるわけでもなんでもありません。
完全にやられました。
自分である程度考える、やったうえで使う
この点は本当に深く反省しています。
AIの言うがままに実行して大変なリスクを追うことになってしまいました。
まぁ、幸い。
直接的に収益に関わることではないので、時間をかけてそのカテゴリを復活させればいいだけですが、本当にAIは無責任に軽はずみな提案をしてくるなと感じました。
自分である程度考える。ある程度やったうえで使う。
そんなの、書くまでもなく当たり前のことかもしれませんが、つい便利なAIに全幅の信頼をおいて頼り切りになってしまいがちです。
だけどそうすると、ほんとうにそうした思いも寄らない事態に巻き込まれる可能性があるので注意が必要です。
そうじゃないと解決策が見つからないまま、終わる
下手をすると、そうして自分で考えないと、
時間を消費するばかりで解決策が見つからないまま終わってしまうリスクすらあります。
まずはじぶんでしっかりと考える脳を作る。
問題が生じたときに、
「これは何が原因で発生したんだ?」
と自分で可能な限り調べてみる。
その上で、どうしてもわからないことを尋ねる。
でも、人に質問するときも全く同じですよね。
わからないことを質問する。
何がわからないけれどそれも含めて質問する。
・・・では、質問を受ける側もどう答えていいのかわかりません。
自分である程度考える実行する。
その上でわからないことを質問する。
そういうやり方にしないと、いつまでも同じところを言ったり来たりで終わってしまうかもしれません。
要は、
AIに丸投げしないこと
繰り返しになりますが、そんなの本来、当たり前のことですが、そういう気持ちが大切なんだと思います。
そういう思いで取り組まないと、ついどうしても頼り切りになってしまって、解決策が浮かばないまま終わってしまいます。
偏ったAIの意見は下手をするとチャンスを棒に振る可能性すら含んでいます。
アドバイスを受けてもい実行を踏みとどまって、複数のAIに質問する質問文を作ってもらうのが利口
ここ最近、本当にそう感じます。
「これが解決の手段です。」
と言われて、言われるがままにそれを実行すると、あとで痛い目を見る可能性があります。
あとで取り返しのつかない事態に落ちいってしまうかもしれません。
アドバイスを受けて、「これだ!」と思っても踏みとどまって、複数のAIに、
「本当にそれでいいのか?」
と質問する質問文を作ってもらうことが大切です。
つまり客観的な意見を求める。
もちろん自分でもしっかりと考えたうえで。
そうじゃないと大切な機会損失をするどこか、取り返しのつかない事態を招いてしまうかもしれません。
まとめ
そういうことですね。
AIは無責任に軽はずみな提案をしてくる
自分で考える、自分でやったうえでAIを使う
アドバイスを受けても踏みとどまって複数のAIに質問する
これらが大切なんですね。
本当にそう思います。
便利なAIも下手をすると完全にリスクを背負って、逆の結果になってしまうこともあるかもしれません。
まずはしっかりと、そうした状況を鑑みて、考えながら使うのがベストだと思います。
わかりました。
僕もしっかりと考えながら使うようにしてみます。
ありがとうございます。
最後まで読んでいただいてありがとうございます。感想、ご質問等がございましたら、お気軽にコメントをどうぞ(^^)
もしよければ、こちらから応援をお願いします。
よりお役に立てる記事を書けるようがんばれます(^^)
コチラ↓↓をクリックしてapaを応援
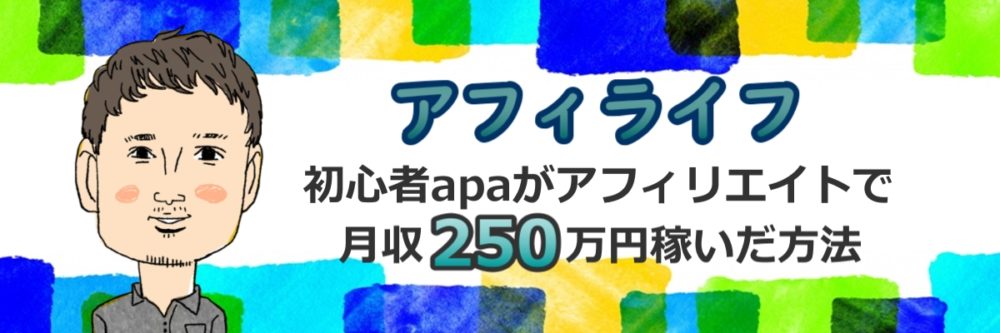






コメント