こんばんは!
いつも応援していただき、ありがとうございます。
apa(あぱ)です(^^)
今日は『AIは日進月歩』について書いていきます。
エーアイは本当に難しい
うーん、AIって、本当に難しいな・・・
自分の中では結構頑張っているつもりなんだけど、なかなか思うように動作を安定させることができないな・・・
どうしたんですか?
a男さん。
動作が安定しないとかどうとかって、なにかあったんですか?
あ、apaさん。
そうなんです。
ここ最近、どんどんエーアイを使って作業する機会が増えんたですけど、AIって、やればやるほどわからないことがどんどん増えていくっていうか、どんどんアラぬ方向に行ったりすることも多いので、扱いが難しいなと感じていたんです。
なるほど、確かに。AIの扱いってなれるまでがすごく大変ですが、慣れてからもやることが多いのでとても苦労しますよね。
AIって本当に難しいなと思います。
自分の中では、この方法でいいと思っていることも、最初は良くても使い続けていくうちに、様々なアラが見えてきたり、様々な問題が生じたりしてきます。
そういうのに対処して、ひとつひとつをただしていくのって、意外と手間で難しいものなんですよね。
そう考えると、AIは本当に一筋縄ではいかないなと感じます。
少なくとも、AIを
「楽をするためのツール」
と考えて利用しようとしても大抵はうまくいきません。
たいていは失敗します。
確かに、楽しようと思えば楽をできてしまうのですが、そうすると本末転倒というか、
大事なポイントをおろそかにしたまま進化してしまうことになってしまう、
記事を執筆してしまうことになるので厄介です。
僕自身、毎日AIを使って作業はしているものの。
その中で、「あれこれってどうなの?」
と思ったものの、毎日の作業の中で気づかずに、
そのままにしてしまっていたことがありました。
ここ最近、それを正してみて、
「あ、今まで間違えたまま進んでいたのか・・・」
と気付かされたことがありました。
そういうのは、非常に厄介というか、難しい問題ですね。
ともあれ、そういうAIのりようによる問題。
色々とあると思いますが、まず一番忘れてはならない大事なことは日進月歩。
そうして少しずつ進歩させていて進化させていくしかないんだと思います。
以前同じようなことを「プロンプト」に置いても書いたのですが、プロンプトに限らず、
AIの利用全般において言えることだなと思い、改めて筆を執っている次第です。
AIは日進月歩
うーん、どうしたら、もっとAIをうまくマスターと言うか、使いこなすことができるんだろうな・・・
確かに、本当にAIのりようって難しい部分が多いですよね。
一筋縄ではいかないですよね。
結局そういうのは、一発で着実に、すぐにうまくいくということはほとんどないので、
毎日自分で少しずつ調整して進化、進歩させていくしかないんだと思います。
少しずつ進歩させていくしかない
本当にそう思います。
AIの設定。
AIの「命」はプロンプトにあると言えます。
しかしそれだけではなくて、細かい使い方一つ取っても、使い方を少し変えるだけで印象が全く異なったものになる場合もあります。
そういう意味でも、難しいポイントが色々あるなと感じます。
authorのアバター
これは直接AIとは関係ないことで恐縮なんですけど、
以前もこのブログで書いたように、
Googleに構造化データを送信するうえで、
さらにその送信した「ライター」の情報を記事内で登録するためには、authorというプラグインを使うのが便利です。
うまく連動して、
執筆者情報をGoogleに送信してくれる上、
記事上に「ライター」としての情報を掲載することができます。
しかし、自分自身。
その「author」の設定がまだまだ甘かったと反省しています。
ひとつは、
authorの「執筆者情報」の部分をh4で記事内に出していた
もう一つは、
「アバターの画像」を小さく表示していたためスマホではすごく見えづらくなっていた
ということです。
authorというプラグインを使えば、記事内に、執筆者の情報を掲載することができるのですが、いわゆる
「この記事を書いた人」
という文字。
これが、h4になっていると構造上、ちょっとおかしな話になってしまいます。
というのは当然、長いSEOの経験でわかっていたのですが、つい、authorの設定でそのままそれを継続してしまいました。
この動画、
を見て、
「あ、そうだよね。」
と改めて気付かされました。
反省反省。
ということで、「この記事の執筆者」の部分は上記動画で語られているように、
「div形式」に変更することにしました。
ディープリサーチの計画確認・編集のプロンプト
これは昨日の記事でも書いたことなんですけど、
【ディープリサーチは便利だけど危険】本来のキーワードの意図と近いリサーチをしてくれるか、計画の編集を押す勇気
僕自身、記事を執筆する前に、よりよい記事にするためディープリサーチで情報を集めてそこから記事執筆のプロンプトに移行しているのですが、
恥ずかしながら第1段階のディープリサーチ。
完全に、geminiが提案してくる計画にそのまま、
「リサーチの開始」を行ってしまっていました。
これ、大いに反省するところです。
geminiのディープリサーチはとても便利なんですけど、
「計画の作成」はまだまだとても甘いです。
まぁ、そのディープリサーチのプロンプトそのものの問題の可能性もあるんですけど・・・
ただ、計画はそのまま提出されたものを鵜呑みにしてしまうとアラぬ方向にリサーチされることになってしまいます。
きちんと、計画の内容を確認して適切に導いていかないと、
そこからそもそもの「記事執筆の方向性」が大きくズレてしまいます。
「ダイエットで痩せる方法」
を知りたい方向けの記事なのに、
「ダイエットで痩せた方の客観的なデータ集め」
で終わってしまう可能性すらあります。
やっていく中で疑問に感じたこと、違和感を拾い上げて進歩させていく
そんなふうに、AIの作業はどうしても、
「流れ作業」
になってしまいがちな傾向になりますが、
やっていく中で疑問に感じたこと、違和感を拾い上げて進歩させていかないと
間違った方向、アラぬ方向に進んでしまう危険性があります。
やっていく中で「流れ作業」で済ませないで、違和感をきちんと拾い上げる、
違和感のアンテナを張っておく
事がとても重要だと感じます。
そうしないと、ただ流されるがまま、
流れのままに作業するばかりで、肝心の記事が本来の目的とは異なる方向に進む可能性、大です。
自分自身、そのまま、つまり「間違ったまま進んでしまった記事」がいくつかあります。
大いに反省。
AIを活用してもいいので、改善案がないか常にもさく献灯することが重要だと思いました。
まとめ
そういうことなんですね。
AIは日進月歩させていくしかない
つかっていくなかで違和感がないか常にアンテナを張っておく
そのままにせず、きちんと改善をする
これらが大切なんですね。
そうですね。AIによる作業はなんだかんだ言ってやることが多いので、下手をすると、失敗につながる可能性もあります。
常に改善策、改善案がないか、アンテナを張っておくことが大切と言えます。
わかりました。
僕自身、よりよくするために常にアンテナを張って作業していきたいと思います。
ありがとうございます。
最後まで読んでいただいてありがとうございます。感想、ご質問等がございましたら、お気軽にコメントをどうぞ(^^)
もしよければ、こちらから応援をお願いします。
よりお役に立てる記事を書けるようがんばれます(^^)
コチラ↓↓をクリックしてapaを応援
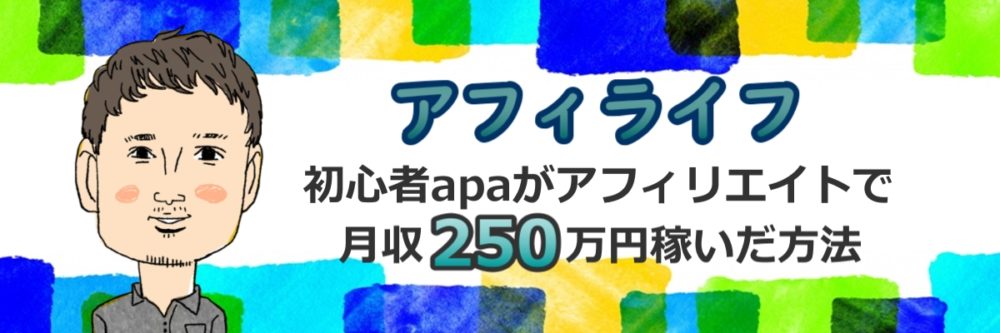






コメント